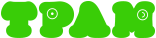安藤裕康
国際交流基金 理事長
TPAM – 国際舞台芸術ミーティング in 横浜に変わらぬご支援をいただき深い関心を寄せていただいている日本国内および海外の関係者の皆様に、心からお礼を申し上げます。
国際交流基金アジアセンターが主催団体の一つとなり、TPAMのアジア・フォーカスがスタートしてから今回で5回目となります。今や、TPAMは名実ともにアジアにおける重要な同時代舞台芸術のプラットフォームのひとつとしてその地位を確立し、年々多数のプレゼンターやアーティストが参加するようになりました。TPAMでの上演を契機にアジアの作品が世界に招へいされ、新規の共同制作企画が生まれ、複数のネットワークが形成され、アジアにおいて持続的な交流や協働が形を成しつつあることを、大変喜ばしく思います。
TPAMでは、今年も日本、シンガポール、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピンなどのアーティストの作品を取り上げ、多様な公演プログラムを展開いたします。国内・海外から多くの団体・個人の参加のもと、ネットワーク形成・拡充・協働のためのミーティングと、公募制のTPAMフリンジもさらに充実したものとなっています。そして国際交流基金アジアセンターはアジアにおける更なる協働をめざし、引き続きアジアを中心に世界から40名ほどのプレゼンターを招いております。
今後TPAMが舞台芸術における新しい価値の創出を可能にする画期的な場として有効に機能するとともに、世界の舞台芸術の担い手の間で広く共有され、持続的な協働が実践されていくことを願っております。

玉村和己
公益財団法人神奈川芸術文化財団 理事長
私どもが主催団体として参画する「国際舞台芸術ミーティング」が2011年に横浜で開催されるようになってから、今回で9回目を迎えました。改めて、この催事を支えて下さる多くの皆さまのご尽力に深く感謝申し上げます。
主催公演である「TPAMディレクション」の主会場ともなるKAAT神奈川芸術劇場では、アジア各国の気鋭のアーティスト達による、演劇・ダンス・音楽・アートの枠にとらわれない舞台芸術の新たな可能性について示唆した作品が上演されます。当劇場では全施設を会場として提供すると共に、創造型劇場としての特性を活かし、アーティストの創造を最大限にバックアップし、この催事に取り組んでおります。
「芸術の創造、人材の育成、賑わいの創出」というミッションを掲げる当劇場も、引き続き、芸術文化を支える一翼を担っていけるように邁進してまいります。また、この催事が参加される皆様の芸術文化との新たな出会いと交流の場になることを心より願っております。

近藤誠一
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 理事長
横浜で9回目の開催となりますTPAMは、舞台作品の上演に加え、様々な交流プログラムが特徴的で、ネットワーキングを目的に国内外から舞台芸術に関わる人たちが集まるユニークなイベントです。市民の皆さまにとっても、アジア最先端の舞台芸術の動向が体験できるとともに、シンポジウムやプレゼンテーションを通じて、芸術と社会の新たな側面を垣間見ることのできる貴重な機会でもあります。
また、TPAMのプログラムは、歴史的建造物や、古い建物をリノベーションした会場などでも行われ、普段、劇場や展覧会場に足を運ぶのとはまた一味違った芸術との関係性を提案します。芸術や文化のもつ「創造性」を生かし、横浜市および当財団が力を入れて取り組んで参りました豊かで魅力的な街づくりが、こうしてTPAMに寄与することができますことを大変うれしく思います。
今回も、TPAMで国境、世代、ジャンルを越えて舞台芸術に関わる人たちが出合い、新たな可能性を拓くことを期待いたします。

丸岡ひろみ
国際舞台芸術ミーティング in 横浜 ディレクター
PARC – 国際舞台芸術交流センター 理事長
TPAMは今回、新たな拠点で実施します。インフォメーションデスクが設置され、トークやシンポジウムの拠点となるKosha33は、「様々な人がコラボレーションし、新たなカルチャーとライフデザインが生まれる公共の場」として、2018年4月に神奈川県住宅供給公社ビル内に開設されました。また、グループ・ミーティング、スピード・ネットワーキングの拠点となる横浜市開港記念会館は、港町横浜を代表する歴史的建造物で、公会堂として市民に親しまれ、横浜トリエンナーレの会場としても使われるなど芸術に馴染みの深い施設でもあります。これらの会場は、鉄道の駅、KAAT神奈川芸術劇場やTPAMフリンジの横浜会場へのアクセスも良く、TPAMの新しい可能性を開いてくれると期待しています。
さて、TPAMは2005年に、「同時代的=コンテンポラリー」な舞台芸術に取り組む「プロフェッショナル」を主対象とする催事であると自己定義しました。それから10余年の間、この定義に立脚したプログラムを展開してきましたが、最近、この2つの概念を再考するべき時期が来ているという実感があります。
この秋に訪れたミュンヘンでのIETMの大会やオーストラリアのフェスティバルで出会った20代、30代前半の若者たちには、「コンテンポラリー」という言葉はマーケット的に響くと言われました。あるいは、ここ数年頻繁に訪れているアジアでは、この言葉に付随する暗黙の了解が通用しないことも多く、何を言うために自分はこの言葉に頼っているのか考えさせられます。
私はよく、舞台芸術はライブ・パフォーマンスである以上、原理的に同時代にしか存在し得ないという言い方をしてきました。つまり、良くも悪くも、「同時代的な舞台芸術」という言い方は同語反復であるということです。この同語反復には、舞台芸術が良くも悪くも自動的に「時代を映す」「時代に応答する」ものであるという主張が含まれています。また、商業的エンタテインメントや伝統芸能の既存のシステムとTPAMのターゲットを区別するためにもこの語は便利でしたし、この語に固執することは保守化に対するある程度の予防策としても機能していたと思います。
しかし近年、複製技術を取り入れるというレベルではなく、複製技術が中心的な役割を果たす「パフォーマンス」作品、作者やパフォーマーがこの世に存在しなくなっても上演が(少なくとも技術的に)可能な作品を紹介することが増えてきました。それを舞台芸術と呼ぶのであれば、ライブ・パフォーマンス性、いわゆる「いま・ここ性」は、このジャンルの「同時代性」を自動的に保証する本来的な性質とは言えません。
また、持てるもののリベラルな視点で捉えられるものだけを映し、持たざる者、奪われる側の視点は隠蔽されるような世界観、あるいは同時代の感覚を映してはいても、時代の矛盾を指摘し共有するだけで、それを批評したり乗り越えて回答を出すというリスクを負わない表現、そういったものの総称として「同時代的」という言葉が定着してしまった感があります。20世紀以降の芸術は「美」という概念を批判し、ほぼ殺してしまいました。しかし「同時代的」という語は今や、かつて「美」が持っているとされた特権性や排他性を、より洗練された形で備えているとさえ言えるかもしれません。この語の使用を今すぐやめれば済むということではありませんし、技術的にもそれはまだ難しいのですが、今年のTPAMディレクションのプログラムが、それに代わる言葉/概念を生み出す/探し出すための一歩ともなればと思っています。
日本では最近、「フェスティバル」というものは欧州から輸入されたスタイルであって、それを日本の環境に適用するのは不自然であるという意見を聞くことが増えています。日本には日本固有の、昔からあった祭があるというのです。しかし、もちろん欧州にだって、コミュニティに根付き宗教と寄り添ったその地固有のフェスティバルは無数にあります。国際演劇祭というフォーマットは、第二次大戦後に演劇人たちが勝ち取ったものであり、自然に発生、発展したものではなく、それに従事する人たちの尽力と専門性があって現在に至っているはずです。
ポピュリズムの台頭、ソーシャル・ネットワークの凄まじい広がりなどを背景に、「市民」を人質にとることで批評を不可能にするようなプロジェクトが散見されるのは、特に都市型のフェスティバルや劇場の新たな特徴のように思います。そのようなプロジェクトの大きな特徴のひとつは、専門性が要求されないということです。であれば、私たちはいったい何なのでしょうか。ある大手ITグローバル企業の採用基準は「いい人」かどうかであると聞いたことがあります。私たちは単に「いい人」になってしまったのでしょうか。
圧政などで苦しんだ庶民の癒しのために実施された、その時だけはお上から「目溢し」される村祭りの復活ではなく、特権的にしか芸術観賞が許されない時代を強い意志を持って乗り越え、思考の場として自らを解放したフェスティバルや劇場の存続、あるいはそれらの理念を引き継ぐ機会や運動の創出は、我々の重要な使命のひとつではないでしょうか。そのためには、どのような新たな専門性が要求されるのでしょうか。2005年以来、TPAMには独立系のプロデューサーや制作者、アーティスト/カンパニーのマネージャー、フェスティバルや劇場のプログラマー、支援団体や公共団体の方々など、職種の垣根を超えてさまざまな「プロフェッショナル」が世界中から集まっています。その皆様が十分に出会い話せる9日間になるよう、スタッフ一同取り組んでいます。
末筆になりましたが、TPAMに快く会場を開いてくださいましたKosha33の皆様をはじめ、関係者の皆様に心より御礼を申し上げます。

Photo by Hideto Maezawa